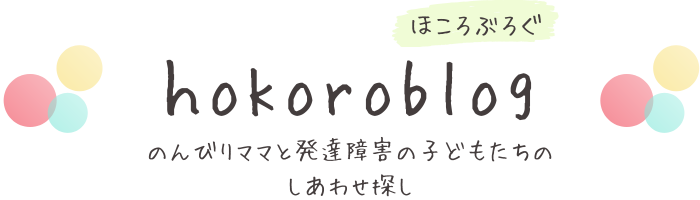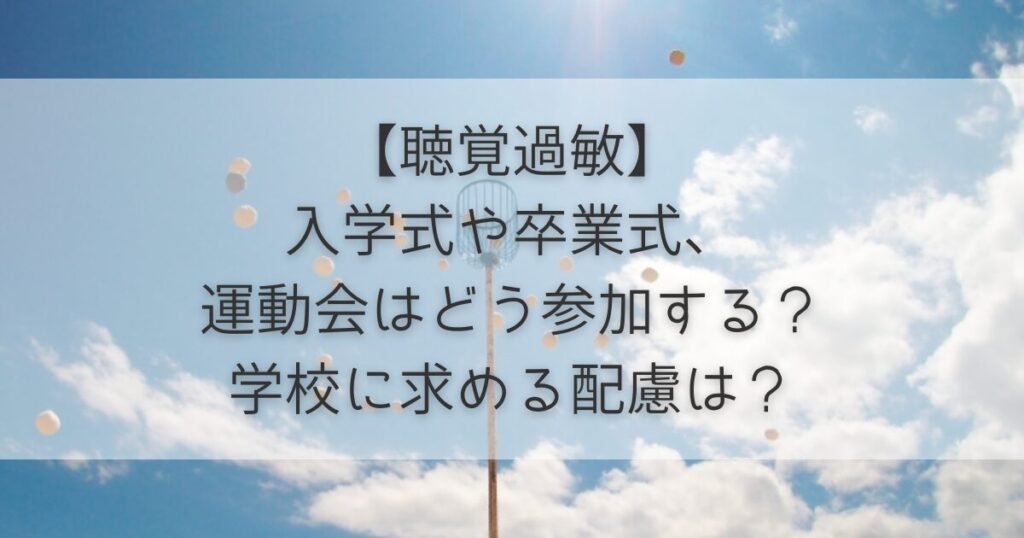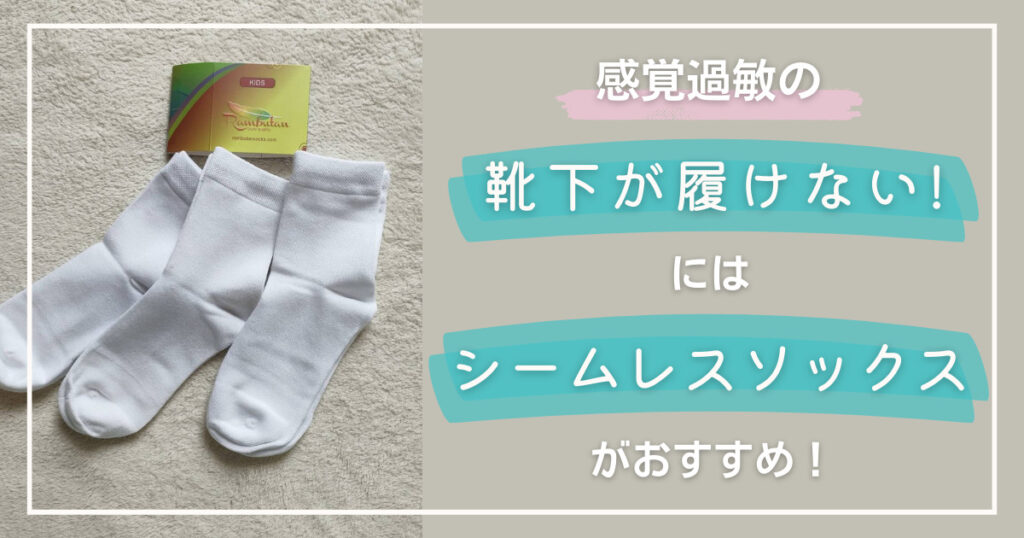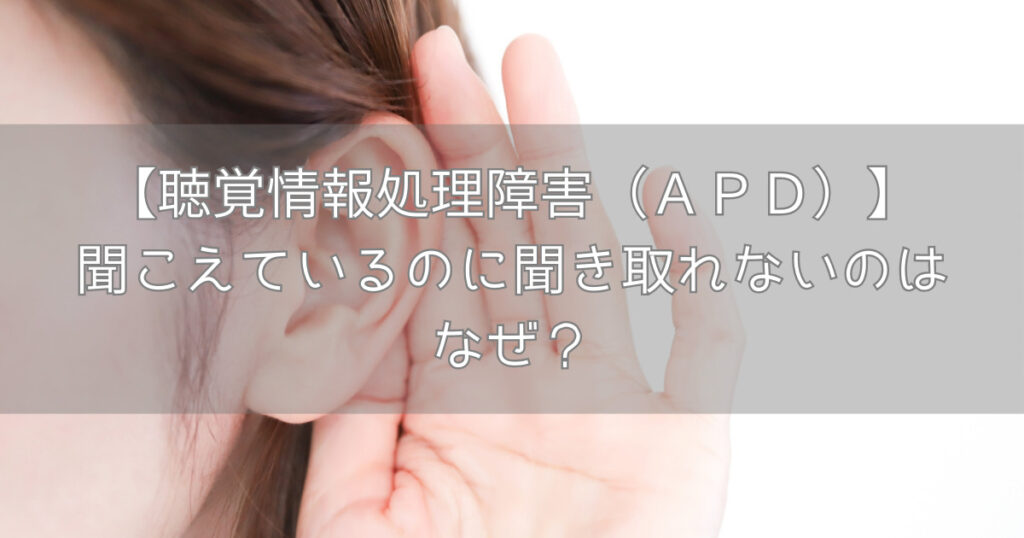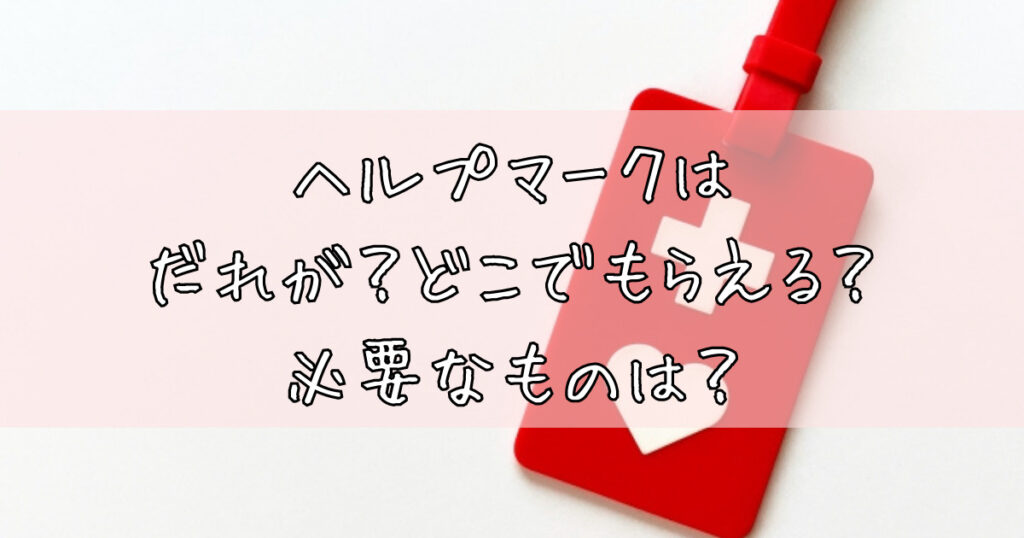感覚過敏のあるお子さんにとって、学校行事は苦手なことが多いのではないでしょうか。
わが家の次男・いくらも様々な感覚過敏を抱え、入学式や運動会などの行事があるたびに、学校と連携し協力を得ながら、どのように対処すべきか参加方法を検討してきました。
今回は特に聴覚過敏に焦点を当て、学校行事における対策や学校に求めた配慮について、わが家の実体験をご紹介します。
感覚過敏の症状は一人ひとり異なり、状況や環境も様々です。
私たちの経験が直接的な解決策となるかは分かりませんが、同じような状況に直面する方にとって少しでも参考になれば幸いです。
参加することがベストではないけれど、参加できたらちょっぴり自信になるかもしれない。
不安や期待を抱える方々に、この経験がお手伝いになれば嬉しいです。
\成長期の味方!美味しく手軽に栄養補給/
子供の成長をサポートする栄養素がたくさん入ったノビルンは、味覚過敏で偏食なわが家の次男も愛用中です。
下記記事ではノビルンの詳細をご紹介していますので、良かったら参考にしてくださいね。
目次
聴覚過敏のある子は学校行事が苦手

聴覚過敏は様々な音が大きく聞こえ過ぎてしまうなど、聞こえ方に過剰な反応が出る感覚過敏です。
音の取捨選択ができず様々な音が流れ込んでくるため、大変なストレスを感じやすく、とても疲れてしまいます。
入学式や運動会、学芸会、合唱コンクールなど、学校行事は大きな声や音楽にあふれているため、聴覚過敏のあるお子さんが苦痛や不安を覚え、「学校行事がつらい」、「行きたくない」と思うのは無理もないことですよね。
どのようにしたらお子さんが不安なく参加できるのかを、学校側としっかり話し合いましょう。
一度しっかりと話し合うことで、その後の行事の際に学校側から提案してもらえることもありますよ。
あらかじめ対策を立てることで見通しが立てば、親も子も安心できますよね。
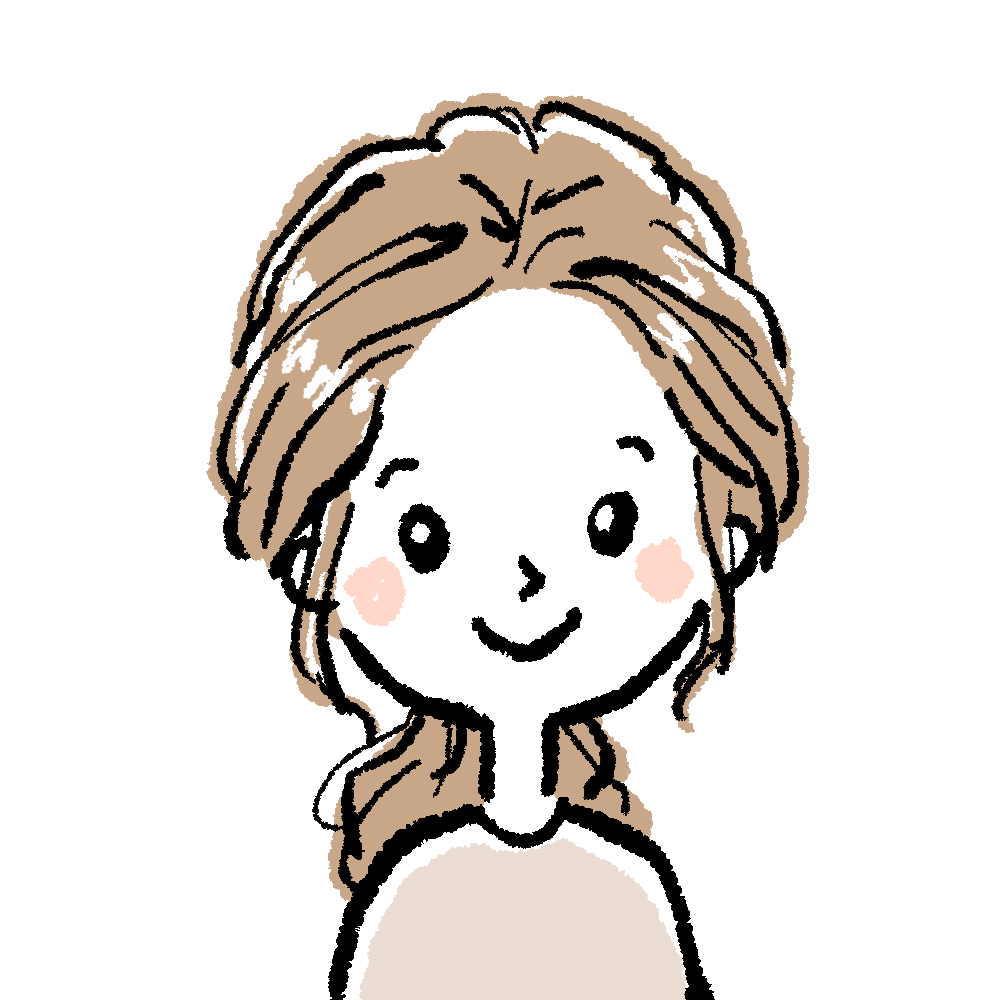
親もハラハラしてしまいますからね
学校によっては、感覚過敏の配慮が異なる可能性があります。 また、お子さんが通常級か支援級かによっても受けられる支援や対応が異なるかもしれません。
いずれにせよ、できる限りお子さんの気持ちを最優先に考えましょう。
感覚過敏はストレスや疲労の影響を受け、症状が強く出てしまうことがあります。
逆にストレスや疲労を抑えることが出来れば、過敏さが和らぐこともあるのです。
今年は参加できなくても、来年は参加できるかもしれない。
成長と共に状況は変わります。その時々の状態で無理のない参加の方法を考えていきましょう。
ときには、無理せず参加を見送るなどの判断も必要になるかもしれません。
入学式・卒業式での配慮

入学式や卒業式では吹奏楽の演奏は不可欠なものです。
吹奏楽の力強い演奏には胸を打たれますが、聴覚過敏のあるお子さんには大きく響き過ぎてしまいます。
大きな負担なくできる対策として、イヤーマフや耳栓の装着があります。
イヤーマフや耳栓の遮音効果は聴覚過敏のつらい症状に有効です。
しかし体育館のような屋内での演奏は音が響くこともあり、イヤーマフをつけていても音が気になる場合や、そもそも触覚過敏もあるためイヤーマフ・耳栓がつけられない場合もあります。
次男・いくらはイヤーマフは着けられますが(耳栓はダメ)、強いストレスを抱え聴覚過敏の症状が強く出ていたころは、イヤーマフを着けても大きな音を嫌がっていました。
おっきな音いや~
お子さんが在校生の場合
イヤーマフや耳栓を使用して参加する。
吹奏楽の演奏があるときは式場の外で待機し、終わったら席に着く。
イヤーマフや耳栓があってもつらかったり、そもそも触覚過敏もあるためイヤーマフ・耳栓ができない場合には、演奏時は式場の外(廊下等)で待機する方法もあります。
入場の演奏が終わってから着席する、退場の演奏が始まる前に退席するなど、お子さんや先生と相談してみてください。
支援級のいくらは出入り口付近に座席を置いて、先生が声をかけて移動させてくださいました(仲間たちと一緒に)。
通常級のお子さんでも、補助の先生が側について移動していたお子さんはいたようです。
もしも先生が付き添うことが出来ずお子さんがひとりで動く場合には、練習の時から「出る・戻るのタイミング」や「どこを通って動くか」などをしっかりと確認し、不安なく参加できるとよいですね。
どの程度ならお子さんが苦痛を感じずに参加できるか、学校と連携を取りながら探って行きましょう。
とはいえ、普段は通常級でみんなと同じ動きをしているお子さんや、中・高生のお子さんは抵抗を感じるかもしれません。
その場合は、無理して参加しなくても良いのかなと思います。
いくらは上記のような方法で参加できたこともありましたが、休んだこともありましたよ。
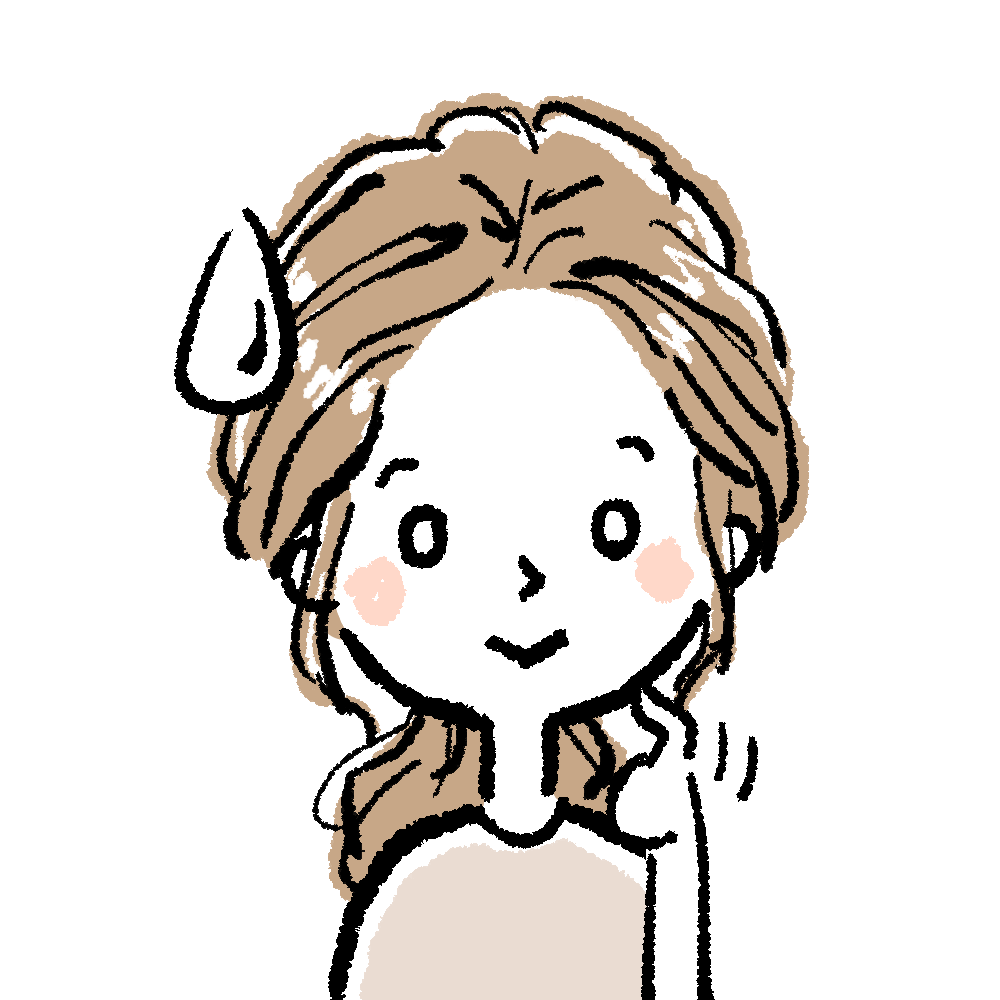
こう言っては何ですが、我が子のイベントではないので、つらさを我慢してまで参加する必要はないのではないかと考えています
もしも出席日数に不安があるのなら、式には参加せずに出席だけ取って帰るなど、学校と相談してみましょう。
\DHA・EPA・GABA配合で集中力・落ち着きをサポート!/
参加できるか? 悩んだ兄の卒業式
いくらは、小学校入学時は通常級に在籍していましたが、ストレスから徐々に体調を崩すようになり、その後発達障害の診断を受けました。
さらに、強いストレスからくる感覚過敏の様々な症状が顕著になり、結果的に支援級に移動することになりました。
その当時のいくらは、イヤーマフをつけても大きな音を嫌がり、人がいると不安を感じるため、全校生が集まる体育館に入ることが非常に困難な状態でした。
そして、そんな時期に兄の小学校卒業式がありました。
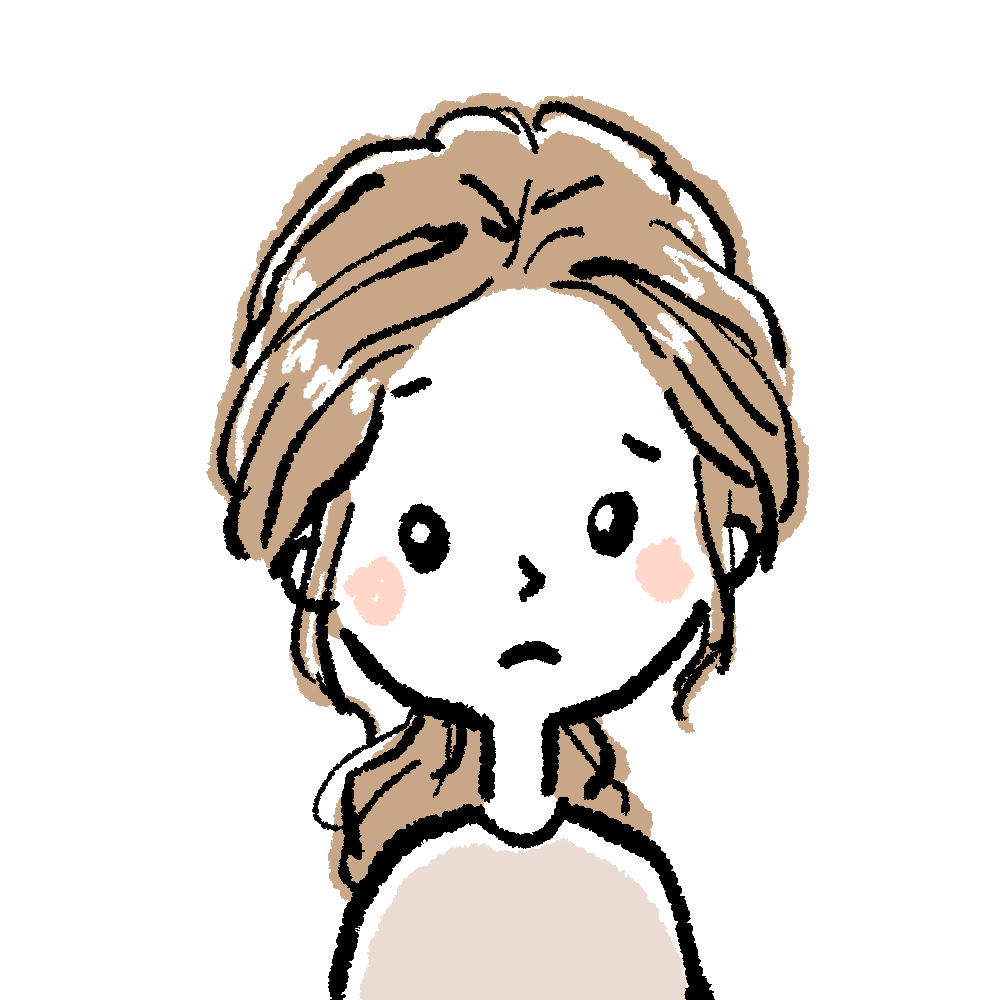
いくらは卒業式に出られないだろうなあ…
いくらが無理に卒業式に出る必要はないと思っていましたが、そうなると、私が長男の卒業式に出席する間、いくらはひとりで留守番しなければなりません。
もちろん、長男の卒業式に出席することは強く望んでいましたが、不安定な状態にあるいくらを一人で残すのは非常に心配でした。
そこで担任に相談したところ、<いくらと一緒に体育館に面した廊下から卒業式に参加する>ことを提案されました。
その廊下にはガラス窓がついた扉があり、そこから式を見ることになりました。 いくらの調子が良ければ扉を開け、良くなければ閉めるなど、状況に合わせて柔軟に対応できます。
さらに、生徒や保護者が出入りする大きな扉が別にあるため、その廊下に保護者が立ち入ることはありません。
人と接することを嫌がっていたいくらも、この状況なら安心できるかもしれないと感じました。
在校生が体育館に集合した後、式が始まる少し前にいくらくんと来てくだされば大丈夫ですよ

とご提案いただいたことも、さらなる安心につながりました。
そして、卒業式当日。
学校へ行くと、廊下には私たちのために椅子とストーブが用意されていました。
まだ寒さの残る時期だったので、先生方の心配りがとてもありがたかったです。
見学する際、近くにいる先生が演奏中は扉を閉め、終わると開けてと、私たちが見やすいように気遣ってくださいました。
いくらは演奏中のみイヤーマフをつけ、時々廊下を走ったり、私とおしゃべりをして(兄の卒業式にはまったく興味を示さずに)過ごしました。
先生方のご厚意のおかげで、いくらに不安を与えず無事に長男の卒業式を見ることが出来ました。
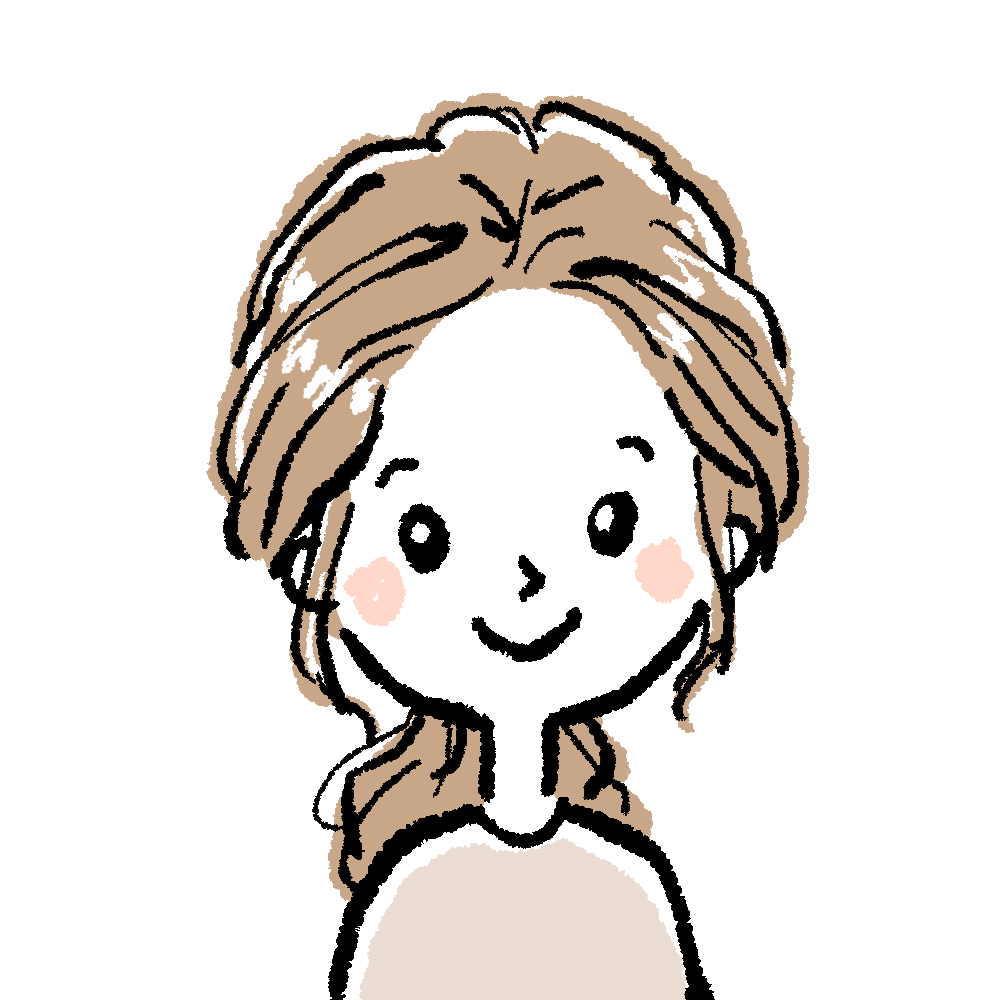
親身になっていくらに寄り添ってくださった先生方には心から感謝しています
お子さんが新入生・卒業生の場合
イヤーマフや耳栓の使用、演奏時の退席などの対策を講じて参加するほかに、個別に式に参加する方法も考えられます。
一部の学校では、不登校や感覚過敏などで通常の式に参加が難しい子供たちだけで式を行う場合もあります。 こうした場合、吹奏楽の演奏や在校生の参加はなく、通常の入学式や卒業式が終わった後に実施されることが多いようです。
また、個別に校長室で入学式や卒業式を行う学校もあります。
不安な方は早めに学校側に相談してみましょう。
わが家の入学式・卒業式は様々
いくらは、小学校の入学式は通常級でみんなと一緒に参加しています。
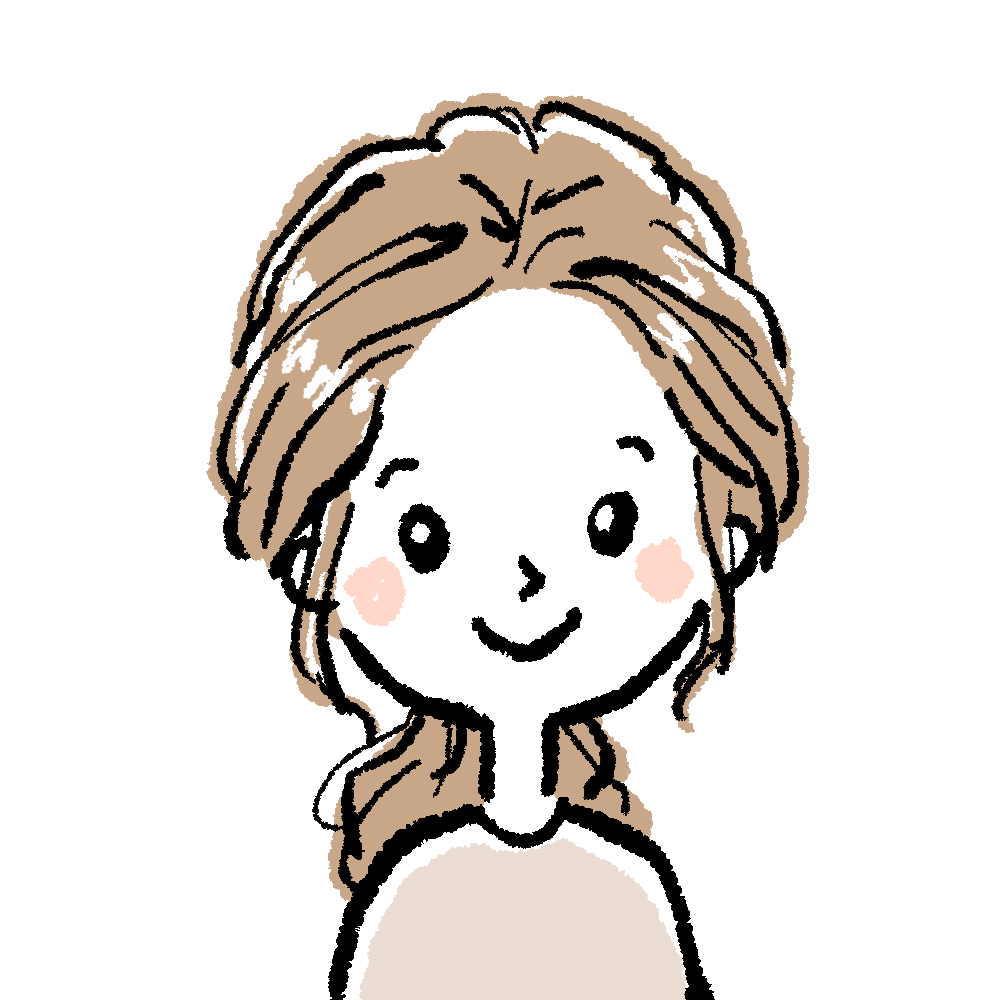
このころは目立った感覚過敏はみられませんでした
その後、支援級に移り、徐々に体調が回復すると同時に感覚過敏も穏やかになっていきました。
高学年になるとイヤーマフの必要性もなくなり、聴覚過敏は「無くなった」と言って良いほど気にならなくなりました。
とはいえ、卒業式に出られるかは不安でしたが…。
最後だから卒業式は頑張る!
と自分で宣言!
不安なく卒業式に参加できるよう、先生といくらで考えながら事前練習を行いました。
- 式の流れ、自分の動きを担任と確認。
- 卒業証書の受け取り方は担任と教室で練習。
- 合唱練習は参加しない。式本番は歌わないが参加はする。
- 全体練習は一度だけ参加する。
結果として、卒業式本番では入場から退場まで、他の生徒たちと同じように式に参加することができました!
吹奏楽の厳かな演奏の中、背筋を伸ばして歩く姿には感慨深いものがありました。
以前の兄の卒業式ではイヤーマフを着用し、廊下からの参加だったことを考えると、いくらがたくましく成長したことを感じ、晴れやかな気持ちで卒業式を終えることができたのです。
立派だったよ~
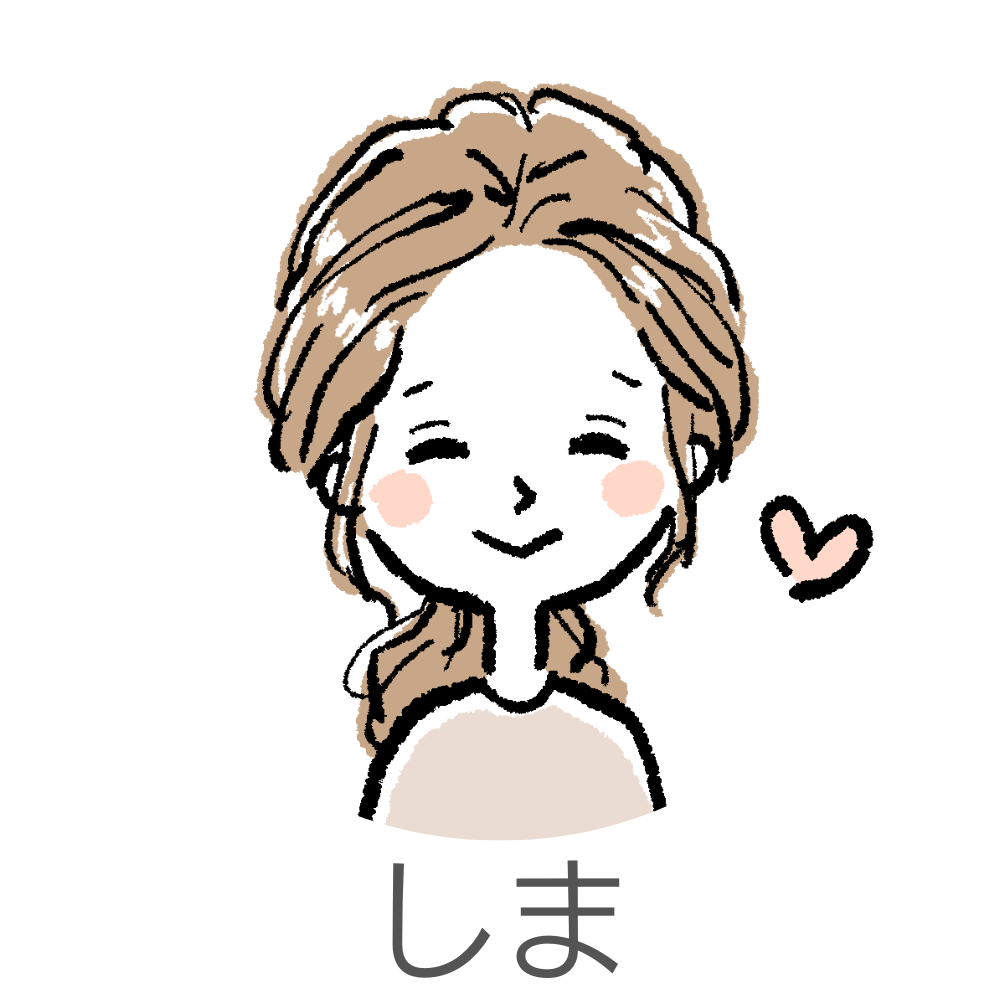
卒業式後、中学の入学式も頑張ると宣言していたいくら。
しかし! 一転して、翌月の中学校の入学式は参加できませんでした。
学校までは行ったのですが、土壇場で「出たくない」と言い出したのです。
いくらと私、そして担任だけの教室でぎりぎりまで様子をみましたが、いくらの気持ちは変わりませんでした。
ここまで来たのに、と残念に思う気持ちはありましたが、頑張りたい気持ちと不安な気持ちの狭間で1番苦しんでいるのはいくらです。
出たくないと伝えるのにも勇気がいったはず。
私はちょっぴり名残惜しく思いながらも、いくらの気持ちを受け入れて「卒業式は参加しない」ことを先生にお伝えしました。
私たちは入学式の最中、春の陽気がぽかぽかの教室でのんびりとお話をして、少し早めに帰ってきたのでした。
中学では新しい環境での緊張や疲れ、今までになかったストレスも出てきているようで、和らいでいた感覚過敏はまた少し強くなってきています。
中学の卒業式はどうなるかわかりませんが、
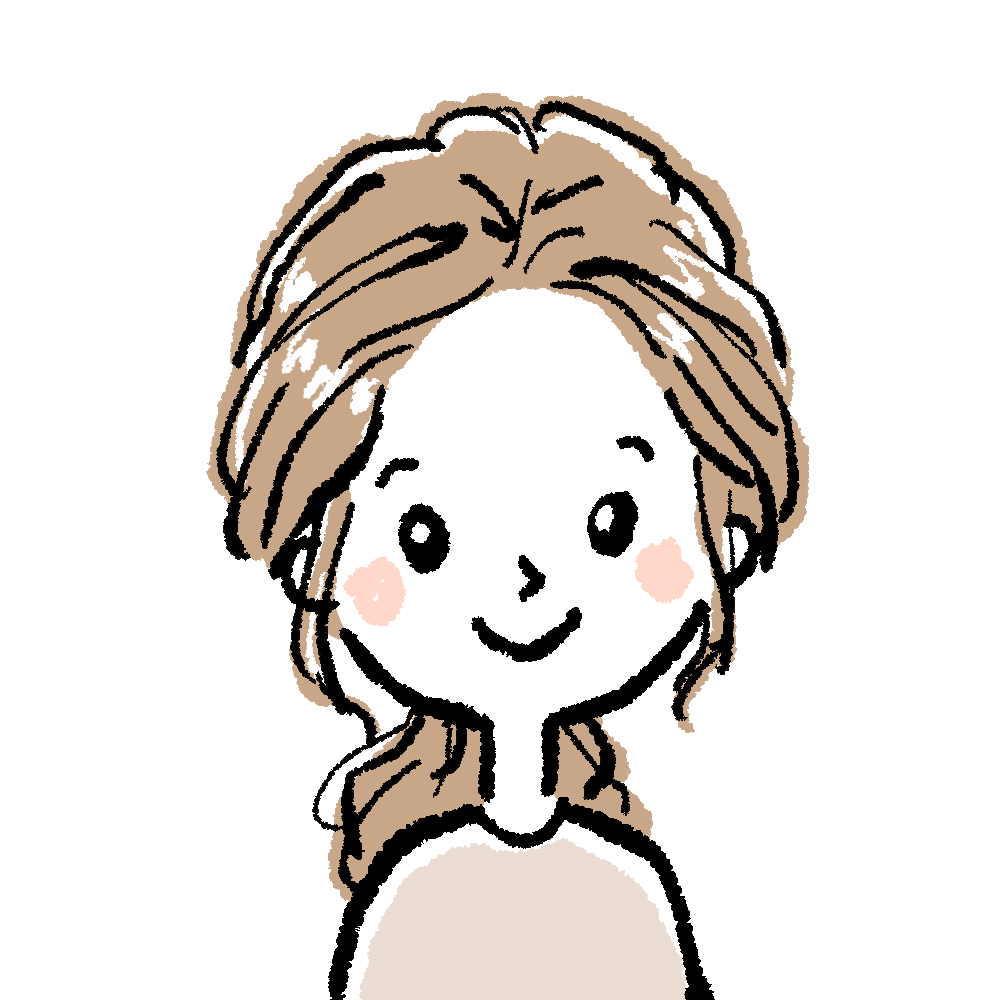
母の気持ちとしては出ても出なくてもどっちでも良い! です
いくらが納得できる選択が出来ればいいなと思っています。
\発達障害の特性に合わせた学習をサポート/
\不登校のお子さんにもおすすめ!/
運動会での配慮
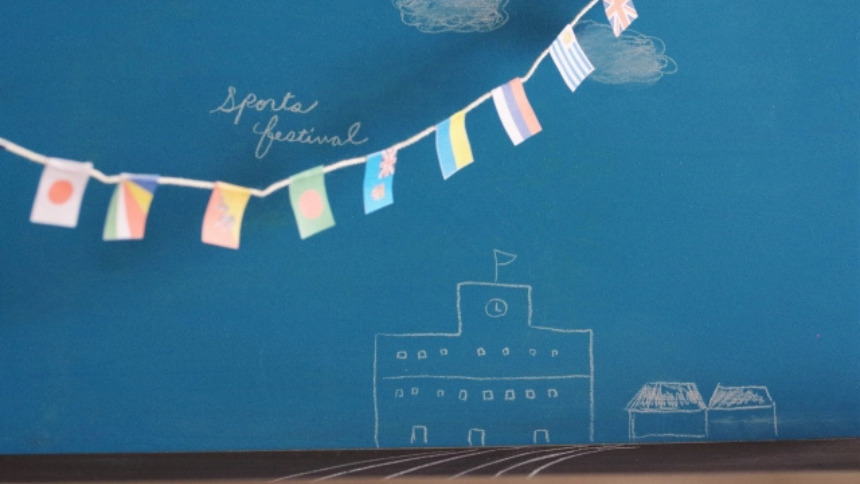
早めにプログラムの内容を教えてもらい、参加できそうなところや参加が難しそうなところをお子さんと確認しましょう。
- イヤーマフ・耳栓を使用する。
- 応援合戦は参加せず離れたところから見る。
- 自分が参加する種目以外の時はグラウンドが見える教室から見学する。
- 自分が参加する種目以外の時は教室で自習などをしながら過ごす。
上記はこれまで学校側から提案していただいたものです。
その年のいくらの状況により、これらを柔軟に組み合わせながら参加することもありましたが、欠席した年もありました。
イヤーマフを付けながらの参加は難しい競技もあり、その場合は無理せず見学していました。
無理なく状況に合わせて参加できるよう、学校側と協力しながら進めてみてください。
それでも学校行事に行きたくないと言われたら

聴覚過敏に限らず、子供と話し合って学校には配慮をお願いし、できる限りの準備をしたにもかかわらず「いきたくない」と言われることはもちろんあります。
- 前日に「やっぱり明日は行きたくない」と言う。
- 当日出発前に「行きたくない」と言う、または体調が悪くなる。
- 頑張って行ったものの学校に入れない、教室まっでは行ったが体育館・グラウンドに移動できない。
受け入れるべきか、背中を押すべきか、正直とても迷いますよね。
ここで頑張れたら自信がつくのでは?参加してみたら楽しめるのでは?という思いがないと言ったら嘘になります。
実際、不安を抱えて参加したのに案外平気だった、楽しめた、自信になったこともあります。
しかしその逆もあり、無理をさせなければ良かったと後悔することも。
また、無理をしないという判断をした場合、子どもは安心した笑顔を見せますが、ただ「休める!」と喜んでいるわけではなく、心の奥底に罪悪感やうしろめたさを抱えてしまうこともあります。 それはきっと、「不安な気持ち」と「がんばりたい気持ち」の両方を抱えているからなんですよね。
どの程度のサポートが必要で、いつ背中を押せばいいのか。
これは本当に難しいです。 私も日々、模索しています。
お子さんが何かできないと言うとき、それは本当にできないし、なかなか前に進めない時期なのでしょう。
時には甘えているように見えることもありますが、大丈夫な時には自発的に動き出すものです。
無理をしないという判断をした場合、私たち親は、子供が後ろめたさを感じることがないようサポートしていきたいですね。
その時にお子さんが、自分はいい判断ができたのだと思えたら、次への一歩が踏み出せるのかもしれません。
まとめ

- 聴覚過敏のあるお子さんは聞こえ方に過剰な反応が出るため、学校行事には苦痛と不安が付きまとう。
- 苦痛や不安が和らぐよう、どのように参加するか学校側と前もって話し合う。
- 準備をしてもお子さんが不安を訴える・行きたくないと言う場合は休ませるという選択肢も考える。
- お子さんの気持ちを1番大切に!
- 聴覚過敏は和らぐこともあり、成長と共に状況は変わる。その時々の状態で無理のない参加方法を考える。
感覚過敏の苦しみは周囲の理解を得るのが難しく、親であってもその理解は容易ではありません。
しかし、子供の気持ちを十分に考慮し、適切なサポートをすることがその先の成長につながるはずです。
学校とも連携を図りながら、お子さんが安心して過ごせる環境を整えていきましょう。
\DHA・EPA・GABA配合で集中力・落ち着きをサポート!/